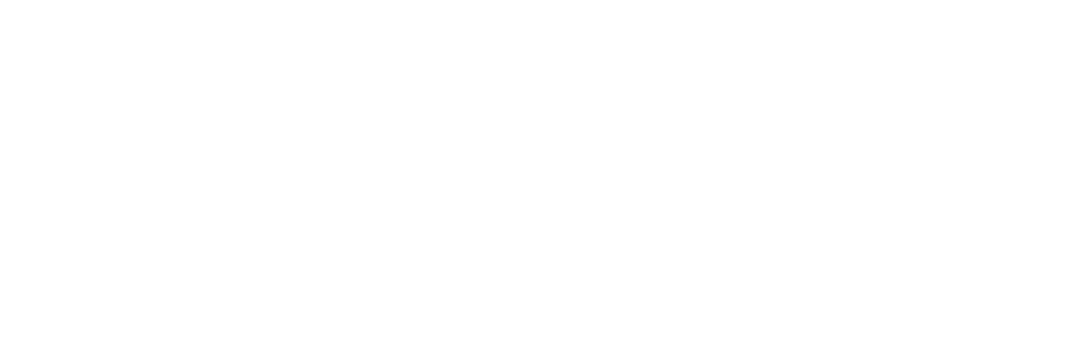1
勅使河原比呂志は正座をしています。きっちり結んだ口、握って腿に置いた手、目は正面を見られません。悪さをした仔犬のようにうつむいて小さく丸まっています。身長181㎝、体重86㎏の体がここまで小さくなるのかと思うくらいです。「恐縮」という言葉を体で表すと、きっとこんな形になるのでしょう。決して美形ではありませんが、誰からも好かれる比呂志の好感度マスクが、この時ばかりは、眉毛も垂れて、口元もへの字、情けなさを全力で表現しているようです。
つい先程までは、爽やかな一日の始まりでした。朝食を終え、情報番組の画面に映る時計に追われるように支度を調え、プレスの効いたソフトスーツで颯爽と家を出ようとする瞬間に、この悪夢が始まったのです。正座でズボンはもう皺だらけです。フローリングの床に敷かれた白いモヘアのラグ、その柔らかな上に座れればまだ良かったのでしょうが
ーーそれ、どかして床にね。
冷たく言い放たれた一言で、板の上に直正座です。足が痛いです。
この家は比呂志が32年の人生でやっと手に入れた男の城です。多摩川ギリギリの立地とはいえ、腐っても世田谷区の一戸建て。それは19坪という猫の額、いや鼠の額のような土地です。価格3980万円のうち、まだローンは3000万円以上も残っているような家です。でも一国一城の主がこれほど小さくなる必要はあるのでしょうか。
「あ、またいたわねぇ……冴木萌」
目の前では、妻の勅使河原鏡子がファッション雑誌をめくっています、片手に持ったハサミが眩く朝日を反射しています。冴木萌は、最近人気のファッションモデルです。
ーー卵は? 遅れそうだから目玉焼きで良い?
そんな暖かい言葉をかけられた15分前が夢のようです。
もう抵抗の出来ない獲物を弄ぶライオンのように、寝間着のアバクロスエットのままで鏡子は、薄笑いさえ浮かべて雑誌をめくっています。
それは好きあって結婚した仲、もう3年経つとはいえ、1歳年上の33歳とはいえ、比呂志は鏡子が好きです。もちろん顔も好きです。母親が沖縄生まれと言うことで、鏡子の人なつこい、良い意味でバタ臭い顔が好きです。化粧のない朝の顔も好きです。でも加虐のスイッチが入った今の鏡子の顔は比呂志は苦手です。怒りだけならまだしも、そこには喜びと恍惚が微妙に混じっているからです
「冴木萌……たくさん出てるわね、ここにも」
彼女が出ている雑誌のページを見つけては、鏡子はハサミで切り抜いていきます。目の前には、大小30枚ほどの冴木萌が積み上げられています。
「貴方!」
ハサミの先端が比呂志の鼻先に突きつけられます。
「なんて言ったっけさっき、もう一回言ってみて」
10分前、テレビを見ながらの比呂志の失言を、こうして執拗に責めあげているのです。
ーーまたCM、冴木萌だよ。良いよなぁ、やっぱり可愛いよな。
思わず口をついて出た時には、もう後の祭りでした。背後に鏡子が腕を組んで仁王立ちしていました。冷酷でいて、しかし楽しいオモチャを見つけたような目で見下ろしていました。そこから家中の雑誌をひっくり返して『冴木萌狩り』が始まったのです。
「まあ、こんなもんかな」
テーブルの上で、切り抜きが小さな山を作っています。
「冴木萌って良いの?」
「いいえ」
「冴木萌って可愛いの?」
「いいえ」
「じゃあ、可愛いのは誰?」
瞬時、返答に詰まる比呂志を、間髪入れず追い詰めます。
「誰っ?」
「鏡子」
そう答えるしかありません。そんな比呂志を見て、鏡子の口元がニヤリと上がります。
「可愛いのは誰?」
「鏡子」
「さん!」
「鏡子さんです」
「可愛いのは誰?」
「鏡子さんです」
「可愛いのは誰?」
「鏡子さんです」
有無を言わせぬ体育会系の口調です。
「じゃあ、まとめましょう。いい?……冴木萌は?」
「可愛くない」
「鏡子さんは?」
「可愛いです」
妙な節に乗せて、もう暗示、もしくは催眠です。
「冴木萌は?」
「可愛くない」
「鏡子さんは?」
「可愛いです」
「冴木萌は?」
「可愛くない」
「鏡子さんは?」
「可愛いです」
「はい、じゃあ火をつけて」
鏡子が、冴木萌の切り抜きを灰皿に乗せます。比呂志はもう、なんでも言うことを聞くマリオネット、指示通りにライターで火をつけます。
朝の日差しに、白い煙が揺らめきます。冴木萌の笑顔が、炎に包まれ昇華してゆきます。小さくうずくまる比呂志、勝ち誇ったような愉悦の微笑みの鏡子、
「はい、じゃあ今日も稼いできて」
「行って参ります」
トボトボと玄関に向かう比呂志です。その背中に鏡子の声、
「帰りに、卵と牛乳を買うの忘れないでね」
もう、何も言い返すことは出来ません。服従するしかありません。なぜなら鏡子は、史上最強の痛い妻「痛妻」なのだからです。
2
「お早う比呂志。大東テレビの新番は? タレント押し込めた?」
50代のメタボ盛りというのにブルージーンズ姿、たっぷりと出たお腹に押されベルトのバックルは、もう前と言うよりは下を向いてます。更にポロシャツの襟を立てるという古いスタイルで、上司である部長の山田太士が比呂志の肩を揉んできます。何やら気持ちの悪い揉み方なのですが、立場上、邪険に払うことも出来ません。山田に言わせると、肩を揉むというのは、相手を服従の気分にさせるこの業界での高等挨拶テクニックだそうです。
「はい、なんとか……セミレギュラーですけど、近いうちにレギュラーに昇格させますよ」
「いいねぇ比呂志ちゃん、どんな手使ったの?」
更に、機嫌良さそうに肩を揉んできます。
「いや、あの番組の木下プロデューサーには、ゴルフに連れて行って頂いたりして、可愛がってもらっているので」
「木下ちゃんね、フーゴル好きだもんね」
フーゴルとはゴルフのことです。そこまで言って、山田が耳元に口を近づけます、仁丹臭い息が比呂志の耳にかかります。
「ズブズブにしちゃって、枕させてもいいよ」
「部長、そういうの良くないですよ」
立ち上がって、比呂志は少し声を荒げてしまいます。
「おぉくわばら、くわばら。熱血漢くん、まあ、頑張ってねぇ」
肩をすくめて、山田は気持ち悪く去って行きます。
「ズブズブ」とは、飲食の接待などで頼み事を断れないようにしておくこと。「枕」とはタレントに夜のお供をさせて仕事を取らせること。この時代に滅多にそんなことはないのですが、この生ける業界伝説である山田は、冗談交じりでいつもこの調子なのです。まあ、こういうことを言うと、ムキになって反論する比呂志が面白くてわざと言っている節もあるのですが。
山田はもう、何食わぬ顔で席に着き、鼻毛を抜きながら朝から雑誌のヌードグラビアをめくっています。それを比呂志がとがめるような視線で見ていると、
「これ仕事だからね、お前も他の事務所のタレントチェックしておけよ」
古いタイプの業界人です。
西新宿にある、排気ガスで汚れた5階建ての自社ビル。すっかり高層ビル群に見下ろされるようになりましたが、テレビ芸能の歴史はここから作られてきたと言っても過言でない場所です。