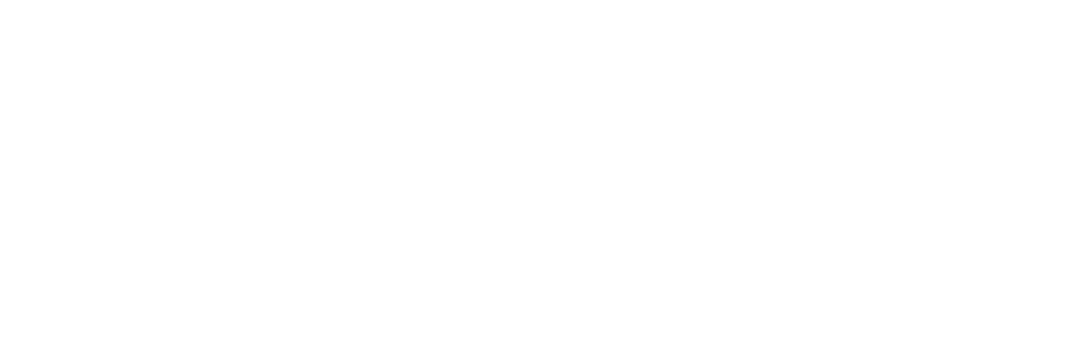「明日香」
比呂志が制止する前に、栗毛色の長い髪をかき上げ、キッと社長を見つめ、もう彼女は言っていました。
「社長、私、あの芝居やりますから」
身長158センチの体が、180センチの社長の前で全く小ささを感じさせません。幼さと妖艶さが同居したような瓜実顔、その顔の大きな部分を占めるアーモンド型の目、長い睫の下で磁力を発する様なその瞳に見据えられたら、比呂志もつい目を逸らしてしまうのですが、MBA社長もただ者ではありませんでした。明日香の眼光を真っ向からうけて、ゆっくりと眼鏡を外し冷たい目で明日香を見下ろします。暗くて冷たい目です。
明日香も決して視線を外しません。
「社長がなんと言っても、絶対にやりますから」
明日香の決意が、部屋の空気を震わせました。
明日香と比呂志が初めて会ったのは2年前、渋谷のスクランブル交差点でした。その日、比呂志はスカウトで、いつものこの交差点に立っていたのです。
芸能プロダクションにとってスカウトは命、次々に新しい人材を生み出して行かないと厳しい芸能界で生き残っていけません。オーエスプロも先代の社長の教えーー全ての社員が一週間に一日はスカウトに出るように、を守ってきました。それは、単に人材確保と言うことだけでなく、街の人たちが、何に興味を持ち、何を楽しんでいるのか、時代の空気を肌で感じるという大切な仕事でもあるのです。さすが叩き上げでここまで来た先代社長の教えは大した物です、比呂志は今でも沖本慎一郎を尊敬しているのです。
人によってスカウトの方法は様々です。街角に立つ者、インディーズのイベントに顔を出す者、登下校時の学生から噂を聞き出す者、でも比呂志は必ず、スカウトはこの渋谷のハチ公前のスクランブル交差点と決めています。それは、比呂志ならではの、この場所で新しい逸材を見つけ出すノウハウがあるからです。
売れるタレントには必ず「オーラ」があります。言葉で上手く説明できる物ではないのですが、持って生まれた人間力、とでもいう物でしょうか。威圧感というが、吸引力というか、見ているだけで気圧されるような空気を放っているものなのです。化粧を落としてで、帽子を目深にかぶっていたとしても大女優というのは空気でわかってしまう、それと同じものです。
比呂志がかつて、これほどまでのオーラが出るのかと衝撃を受けたのが昭和の歌姫「大空ひばり」でした。その日、ビルの7階にあるスタジオで彼女の収録があったのです。スタッフ一同が、それぞれ忙しくスタンバイに飛び回る中、大空ひばりがビルの一階に到着した瞬間、「来た」とスタジオにいる殆どの人が気付いたのです。もちろん、何か連絡が入ったわけではありません、ただ「わかった」のです。「今、到着したな」と一同が目を合わせた2分後に、エレベーターのドアが開いて歌姫が入ってきたのです。そのドアが開いた瞬間に突風のようにオーラが吹き出したのはもちろんですが、ビルの1階に到着しただけで、7階まで感じさせるオーラを持つとは驚きの一言でした。芸能界で10年間仕事をしてきた比呂志ですが「大空ひばり」を越えるオーラは出逢ったことがありませんでした。ただ「明日香」は、彼女を越えるかもしれない物を持っていると、その日、比呂志は感じたのです。
渋谷のスクランブル交差点は、いつものように雑踏に埋め尽くされています。この日本一人通りが激しい交差点、渡りきるまでの91.5メートルに比呂志の特別なオーラ判定法があるのです。それは何も難しいことではないのですが、この子は素質があるかもしれないと見込んだ者が「渡りきるまでに何人の人が振り返るか」をカウントするだけです。芸人でも、女優でも、歌手でも、モデルでも一緒です、オーラを噴出している人には、人は自然と振り返って見てしまうものなのです。2~3人でも振り返れば大したものです、相当なオーラが出ていると判断して良いでしょう。そして、この交差点でのレコードホルダーが、今をときめく「ミッドタウン」でした。まだ素人だった彼らですが、明らかに普通の若者ではない輝きを持っていました。女性を中心に振り返った人数は実に12人、その場で比呂志がスカウトして、あれよあれよとトップスターに上り詰めたのです。今ではスカウトの世界での伝説です。この12人は破られる事はないだろうと思われた大記録です。明日香と出会うまでは。
その日、109側からハチ公側を臨んでいた比呂志ですが、後ろから何やらただ者ならぬ気配が近づいてくるのを感じたのです。これは、先代の教えを守り、毎週1回、10年間、一度も休まず街角にスカウトに立ち続けた者のみが感じることの出来る感覚です。
振り返ると、居ました。この気配の元が、すぐわかりました。それは一見は普通の女子高生でした。学生服を着て、化粧っ毛もなく、長いストレートの髪を一本に束ねている愛想もない女の子でした。身長も高くなく、プロポーションも普通でした。しかし、その目があまりにも普通ではありませんでした。まるでこの渋谷の街中で、野生の豹に出逢ったような衝撃でした。背筋が少し寒くなりました。あれほど力のある瞳は、今までお目にかかったことがありません。そして、彼女は明らかに街の風景から浮き上がっていました。何か、彼女の体自体が透明な膜に包まれているような、本当に地面から数センチ、足の裏が浮き上がっているような感じです。
もしかしたら、新記録が生まれるかもしれない。直感し、彼女がスクランブル交差点を渡るのを、そっと尾行しました。そして、驚くべき事が起きたのです。振り返るのです。すれ違う誰もが振り返るのです。男性はもちろんのこと、女性もほぼ同数振り返ります。男性だけ、女性だけではダメなのです、両性が振り返ってこそ、本当の逸材といえるのです。それにしても道行く人々、みんな振り返るのは不思議な感覚です。彼女はいつものことなので慣れっこなのでしょうが、彼女の後ろをついて歩く比呂志には驚きの連続でした。やはり自分のような凡人には、計り知れない求心力を持つ人がいるのだと痛感したのです。記録が大幅に更新されました。なんと、振り返った人数38人です、横断歩道91.5メートルの中で、すれ違ったほぼ全員でした。この千載一遇のチャンスを逃してはいけない、比呂志の全細胞が叫んでいました。
「スミマセン、怪しい者ではありません」
オーエスプロの名刺を差し出しながら、胸の高鳴りを押さえ比呂志は、彼女の前に立ちました。
彼女と目が合います。思わず心臓が締め付けられるような感覚です。普通の女子高生の前に立っているだけなのに、まるでヤクザの親分の前に立っているような気分です。それだけ鋭い眼光です。決して威圧や恐怖を宿しているわけではありません、あくまで澄んでいるのですが、なにか尋常でない物を湛えている瞳でした。底が知れない目でした。比呂志は、真っ直ぐに自分の脳の中まで見透かされているような気分でした。
「どうか話を聞いてください」
気付いたら比呂志は、思わず土下座をしていました。計算でそうしたわけではなく、その眼光の力に、そしてどんな事をしてもこの子をスカウトしたいという気持ちがそうさせたのです。
午後の雑踏、行き交う人たち、一人の女子高生の前に土下座している中年男……比呂志は後悔しました。どう考えてもこのシチュエーションは奇妙です、怖がらせて、悲鳴を上げさせ、逃げていかせるのに十分です。しかし、彼女は比呂志の予想を遙かに超えた態度を取ったのです。
「まったく……さあ話聞きますよ」
なんと彼女は比呂志の肩を持って、優しく立たせたのです。
普通、女子高生といったら何をやるにも、面倒くさい、うざったい、そうでないとしたら、関係ない、気持ち悪い、です。しかし彼女は、渋谷の街中で見知らぬオヤジに土下座されて、平然とそして、優しささえ持ってその肩に手を置いたのです。なんという器の大きさ、比呂志は感動を覚えました。
タレントとして大成するひとつの大切な要素は「どんな場面でも物怖じしない」です。急に何かするように振られたり、大きな役に抜擢されたりした時に、恥ずかしがったり、疑問を感じたり、躊躇したり、萎縮したり、恐怖したり、プレッシャーを感じたりしないで堂々とやりきること、これがスターになるには大変重要なのです。例え上手くいかなくても、それは良いのです、何より「すぐに堂々とやる」のがスターなのです。正に、この時の彼女といったら、スターの振るまい以外の何物でもありませんでした。彼女は、羞恥、疑問、躊躇、萎縮、恐怖、緊張、どんな反応だって出来るのに、まるで何事もなかったように行動したのです。知り合ったばかりの、いや正確に言うと知り合ってさえもいない比呂志の肩に手を置いたのです。比呂志はまるで「さあ立ちなさい」と、母親に言われているような気分でした。
なんというタレント性、なんという包容力、この子はスターの素質を完全に持っている。そしてそれを自分が育ててみせる。渋谷のスクランブル交差点で土下座から立ち上がり、周囲の好奇の目にさらされながら、比呂志は硬く心に誓ったのです。
「ダメだと言ったはずです」
「あの芝居は絶対にやります」
オーエスプロ2階、第一芸能部フロア。社長と明日香の睨み合いは続いています。